1987年、沖縄でジェームス・ブラウンのコンサートが開かれた。
僕が沖縄を訪れたのは、このときが初めてで、海ではなく、このコンサートが目当てだった。19歳のときだ。
このコンサートが、今思い出すだけでもゾクゾクするほど、素晴らしかった。
ジェームス・ブラウンのコンディションは上々、そして米軍基地の黒人兵が大挙して聴きに来るという、時代も場所も最高のセッティングだったからだ。
そのあと、僕は、市内のクラブ『なんた浜』に嘉手苅林昌の琉歌を聴きに出かけたのだった。
主催者の竹中労一行が到着した午前2時過ぎは、夜更けもいいところだというのに、店内はコンサートから流れた客などでいっぱいだった。このとき、僕は、嘉手苅林昌の歌う八重山民謡を初めて聴いた。
林昌さんが八重山の民謡「とぅばらーま」を歌ったとき、客席から、つんださや、つんだーさー、と、名調子の合いの手がかかった。なんと、山里勇吉である。
気づいて周囲を見てみると、いるわいるわ、照屋林助、国吉源次、登川誠仁など、琉歌の大御所各氏が、皆、ジェームス・ブラウンのコンサートから流れてきていたのだ。
琉歌とジェームス・ブラウン、関係がないようだが、琉歌の各氏は、コンサートに感動し、対抗意識を燃やしたものと見えた。そして、各氏を交えた琉歌ジャム・セッションは、夜が白むまで続いたのだった。
このときの歌の多くは、今にして思うと、八重山民謡だった。ジェームス・ブラウンのソウルに対抗しての八重山民謡だったに違いない。八重山の音楽は、民謡と流行歌が未だ分化していない「原・うた」というような状態にあり、唄本来が持っている情感や躍動感を失ってはいない。だからこそ、ジェームス・ブラウンに対抗して、各氏が直感的に八重山民謡を選んで歌ったのだと考えたい。
このあと、竹中労は、精力的な琉歌の紹介活動に入っていく。僕なども、それによって琉歌を聴き込んだクチだ。あの『なんた浜』の夜の熱気に再び出会うことはなかったけれども、琉歌の魅力を、存分に知ることができた。同時に、「オキナワは日本ではない」という認識も教えられた。
相前後して、喜納昌吉&チャンプルーズをはじめとして、りんけんバンド、ネーネーズなど、いわゆる新世代のミュージシャンが、琉歌の枠を超え、琉歌の可能性をさらにひろげていったのだった。
喜納昌吉は自分の存在に正直な音楽をやろうとし、照屋林賢は自分たちの世代の島歌をつくろうと情熱を燃やしてきた。ネーネーズを束ねる知名定男は、ポップ化した島歌を若い世代に聴いてもらうことにより、本来の島歌のほうへ引っぱる役割を果たした。その成果は、やがて、古謝美佐子の大傑作「童神」を生むこととなった。
皆、連帯しているようでいて、同時多発的でいて、それでも、どこにも属さない自由奔放さがあった。琉歌の作法をキッチリと身体に叩き込んだうえで、そこに安住せず、隷属せず、自由奔放であり続けているのが、沖縄のミュージシャンなのだと思う。だからこそ、ジェームス・ブラウンに感応することができるのだと、僕は思っている。
自由奔放さといえば、登川誠仁さんだ。セイグワーだ。
戦後の沖縄芸能復興の核となった「松劇団」で地謡として唄三線の基礎を身につけて以降、登川さんは、琉歌のエースであり続けた。
一方で、米軍の物資集積所に命がけで忍び込み、銃弾をかいくぐりながら、「戦果」と称してさまざまな物資を抜き取っていた。
沖縄民謡界の表通りだけでなく、戦後の闇の世界も経験しているのだ。しかもウーマクで憎めない性格が人脈を広げ、自身の芸を豊かなものにした。
エレキギターと三線を交互に持った登川さんは、沖縄のジミヘンと呼ばれ続けた。
そもそもが、最高の弦使いなのだ。
そんな登川さんが、昨日、天に召された。享年80歳。
僕を琉歌へと誘ってくれたレジェンドたちは、皆、いなくなった。
合掌。
登川誠仁のこと
 その他
その他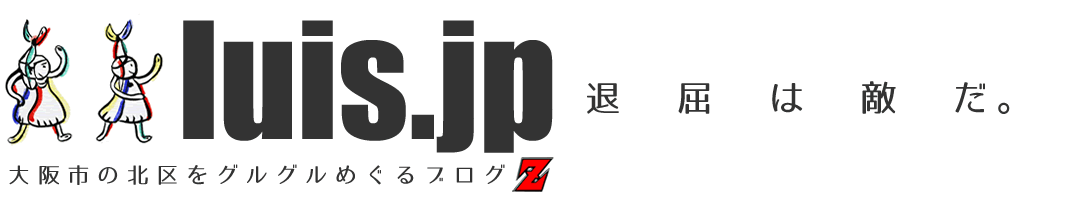


コメント