
昨今のフィッシュマンズの世界レベルでの異様な盛り上がり(もともと、没後もずーっと評価され続けているけれども)を見ていると、デビューから佐藤くんの夭逝までの全期間をリアルタイムで接してきたことは、年長者のまあまあな自慢だ。『米国音楽』に収められていたソノシートで聴いたのがたぶん最初の出会いなので、これはちょっと自慢してもいいと思う。
ファーストアルバムの『Chappie, Don’t Cry』が発表されたのが91年。ミュートビートのこだま和文さんがプロデュースした縁で聴いた。ミュートビートとじゃがたらは、80年代、僕が生きるよすがとしていた数少ない人たちだったから。
こだまさんがプロデュースしたフィッシュマンズのファーストは、こだまさんなのに全然レゲエっぽくなかった。ブルービートには違いなかったが、佐藤くんの歌声に土臭さはなく、中性的、少年的、未成熟で。でも、そこがよかった。なにもかもが、ルーツレゲエの対極にあった。ダブ風味すらなかった。
いち時期、むちゃくちゃ聴いていたのが『Oh! Mountain』。フィッシュマンズで一番聴いたアルバムは、もしかしたら、これかもしれない。ライブアルバムなのに、ライブ素材をスタジオでさらに加工して。そんなことする人って、フランク・ザッパくらいしか思いつかないし、ザッパみたいなことをする人が日本にもいるのか!って思って。ポスト・ライブアルバムというか、アフター・ライブアルバムというか。エンジニアのZAKのスペイシーな感性が炸裂してたし、ナンセンスな音楽コントみたいなのも入っていて、そーゆーことする人もあんまりいなかったので、僕は気に入っていた。ハカセもまだメンバーだったし、スタジオワークの凝りっぷりは、このあたりですでにじゅうぶんに発揮されていた。ZAKがいるということは、そういうことだ。
すでに洋楽だ邦楽だという時代ではなくなっていたけれども、ニルヴァーナ、ソニック・ユース、ダイナソーJrらのオルタナ、グランジ勢、さらにはプライマル・スクリームやハピマンなどの英国製ロックでダンスなマッドチェスターな音が時代の音で、実際それは、80年代の自意識過剰を一掃するような爽快感があった。
そんななかで出てきたのが、フリッパーズ解散後のコーネリアスだ。93年のこと。スタイリッシュさを武器とした渋谷系をさらに推し進めた尖塔の最先端にいたのが、コーネリアスの小山田くんだった。雑誌『ID JAPAN』に、フリッパーズ解散の真相!という、中身がスッカスカの何も語っていない記事が載っていたのを覚えている。渡辺満里奈の取り合いが解散の真相というのは、どこまで本気の話なのよ?(一番イケてたのは、小沢と小山田がデキてて、その仲を渡辺満里奈が裂いたという説ね。笑)
その頃出会ったのが、世間的にはまったく売れてないがロッキンオン界隈では評価がうなぎのぼりだったスピッツだった。スピッツ草野+フィッシュマンズ佐藤+Bフラワー八野の「ひなぎく対談」というピントが外れまくった謎の鼎談がロッキンオンの誌面に載り、僕は爆笑していました。佐藤くんは、「オレ同棲ぐせがあるから!」と頼まれもしないのに謎の告白。
でも、まったく売れていなかったスピッツの、毅然としたそのダサい青さみたいなものには、僕は心を掴まれていた。
ほどなくして発表されたのは、フリッパーズ解散後に1年以上沈黙を保ち、すっかり変わり果てた姿の小沢健二のファーストシングル『天気読み』だった。93年の秋も深まった頃のこと。タワレコで手に取ったレコードの裏ジャケには歌詞全文が印刷されていて、これを読んでグッときて、即買い。歌詞を全文載せるということは、はっきりと言いたいことがあり、自信があるということだ。ジャケ写も、フリッパーズ時代とはまったく違うダサさ全開で、そこがいいなと思った。フィジカルな音楽をまったくフィジカルではない小沢健二がやるというアンバランスさ、少年性が、妙な説得力とリアリティを醸し出していた。小沢健二(まだ「オザケン」ではなかった)登場時の世間の反応は絶賛でも称賛でもなんでもなくて、かなり大きな戸惑いをもって迎えられたと僕ははっきりと覚えているけれども、この毅然としたダサさは、あの時代をサバイヴするひとつの最適解だったのだと思う。しばらくして発表されたファーストアルバム『犬は吠えるがキャラバンは進む』が大傑作だったのは周知の通り(それすらカルト宗教的と言われたのだけれども)。ギターが、ニール・ヤングみたいにぎこちない、いいギターだった。フリッパーズ時代はあんなギターじゃなくて、もっとカッティングがオシャレで音離れのいいギターだった。全体に音がこもっていて、湿っていた。オレンジ・ジュースからニール・ヤングへの変化は、ネオアコだった人が純アコに先祖返りしたみたいだった。それが93年から94年にかけてだったと思う。
次のアルバム『LIFE』は、このアルバムの「偉大なる蛇足」だと、世界を敵に回してでも僕は断言しておく。(そう断言しても、『LIFE』の素晴らしさは、些かも損なわれはしない)
フィッシュマンズは、93年のその年、『Neo Yankees’ Holiday』を発表した。これもまた、毅然としたダサさに貫かれていた。このへんの年代の音楽の僕の当時の評価基準といえば、「毅然としたダサさ」だった。今もそんなに変わらないけど。
前年の92年に発表されたパール兄弟の窪田晴夫プロデュース『King Master George』は強烈なコンセプトアルバムで、悪くはないけれども、フィッシュマンズはまだ迷いの季節にいたと思う。鮮明な像を結びはじめたのは、やっぱ『Neo Yankees’ Holiday』からだろう。
どこかキヨシローを思わせる佐藤くんのボーカルは渋谷系から明らかに訣別していて、レゲエをやっていてもスノッブさに収まらない、自由でのびのびとした感性で貫かれていた。
そういう時代に、人生の卓球がいつのまにか電気グルーブに装いを変えテクノになっていたので、CDを1枚買ってみたら、あの大名盤『VITAMIN』で、当時の僕の嗅覚は百発百中だった。畳はいつの間にかピエール瀧と名乗っていた。
しばらくして、94年、フィッシュマンズは『ORANGE』という、ちょっとロックなアルバムを出した。佐藤くんの厭世気分漂う歌詞は、このあたりで完成したのではなかろうか。ゆるく生きる彼のゆるぎない覚悟(?)もまた、「毅然としたダサさ」だったように、今でも思っている。
流れるミュージック/暗いメロディ/ホコリの匂いのする/見えてる景色/窓枠どおりの
そんな時代の流れに逆らうように起こったショッキングな出来事は、カート・コパーンの自殺だ。僕より下の世代は心に深い傷を負った人もいただろうけれども、僕にとってはもう、まあ海の向こうの出来事というか。
94年、カーネーションはソウルフルで瑞々しい傑作『EDO River』を発表し、オザケンが時代の寵児になった。
左へカーブを曲がると、光る海が見えてくる。僕は思う!この瞬間は続くと!
タモリが絶賛した全肯定の生命讃歌を、オザケンは高らかに歌っていた。後年、それもまた孤独な咆哮だと知ることになるのだけれども。
95年、サニーデイ・サービスが『若者たち』で思いっきりダサい方向へ舵を切って登場し、はっぴいえんどが化けて出た!と人々が口にした。続くシングル『青春狂走曲』『恋に落ちたら』そしてさらに続くアルバム『東京』で、動かしようのない「ホンモノやん、これ」となり、今に至るまで、まったく揺るがず固定された評価となっている。どころか、曽我部くんは今もって、最前線で、永遠とも思える何度目かの創作爆発期が続いている。
で、まったく売れていないスピッツはもはや過去のなにそれ?的なことになっていて、そのスピッツのポリドールに移籍したフィッシュマンズは、印税前払いでポリドールに出金させて設立したワイキキスタジオに入り浸り、あの『空中キャンプ』をつくる。あのアルバムは、もう、「あの」でいいだろう。
96年以降、『空中キャンプ』も『LONG SEASON』も、その次の『宇宙 日本 世田谷』も、もはや毅然としたダサい青さではなく、純度100%の鋼のようなアルバムだ。語るのも馬鹿馬鹿しい、聴けばわかるよ全部、としか言えず、ただただ、頭を垂れてたそがれるしかない。今後1世紀、これらの評価は揺るがないのではないか。と思わせるほどのモンスター。
96年と97年は、フィッシュマンズにとって、ダンス&リズム・ミュージックにとって、永遠に光り輝く黄金色の2年間だ。
あの時代、フィッシュマンズが真ん中にいたことが、魔法だった。
そして、夜のまちを浮遊するような『ナイトクルージング』のあの人は、『ウォーキン・イン・ザ・リズム』のままに月まで飛んでいって月面着陸してしまった。魔法だ。魚たちと僕たちが見た夢。
折に触れて聴くのは、『男達の別れ』。実質的にラストになってしまったライブを収録したこのドキュメンタリーなライブアルバムを聴くたび、なんだかんだ言ってフィッシュマンズには熱い塊のようなものが奥の奥にあったと思えてくる。フリッパーズの解散後に出たライブアルバム『続カラー・ミー・ポップ』にもおなじことを思うので、もしかすると、バンドにピリオドが打たれたあとに発表されるライブアルバムには、そんなことを思わせるなにかがあるのかもしれない。
海の向こうではボアダムスが全人類をマジカルな幻惑に陥れ、ジョンスペはベルボトムを復権させ、RLバーンサイドがエグいブギーを奏で、チボマットはねっとりとエロい果実を囓り、あふりらんぽのオニとピカは谷六あたりでスパイスカレーを食べる僕の前で変な踊りを踊っていた。思い出波止場はデス渋谷系(笑)からムード歌謡に変容し、JOJO広重さんは『君が死ねって言えば死ぬから』と言っていたのに死なずに今も元気に若いおねーちゃんと戯れている。デタミは生あたたかい風を京都から吹かせ、UAはミルクティーを攪拌させ、ASA-CHANGは巡礼に立ち、あらかじめ決められた恋人たちはすでに恋人活動をはじめていたが、中村一義はまだ「状況が裂いた部屋」にいて、くるりはフジロックの暴風雨のなかにいた。ソウルフラワー・ユニオンはアイリッシュトラッドや琉球トラッドの重鎮たちと活動をともにし、マージナルな月の淵を歩いていた。96年と97年はそんな時代だ。今にして思えば、世紀末の音楽は、すでに新世紀に片足を突っ込んでいた。
映画『フィッシュマンズ』を見た帰り。
今さらだけど、この歳になって、フィッシュマンズって茂木の欣ちゃんだよなって思う。フィッシュマンズはもう、さとちゃんよりも欣ちゃんがドライブしている時間のほうが全然長くなった。欣ちゃん、ずっと続けてくれてありがとうな。
あれから22年が経った。HONZIも天に還った。『LONG SEASON』のジャケのあの場所も、今はもうない。長いような、短いような。
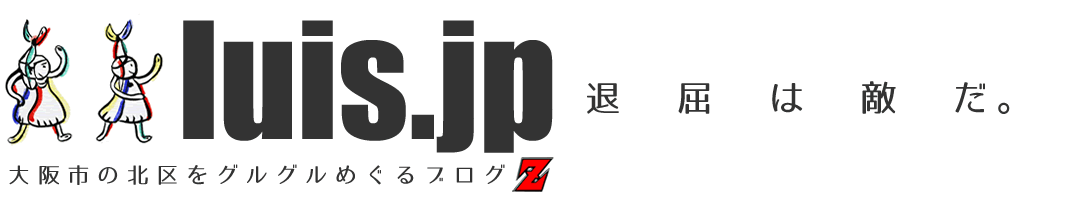

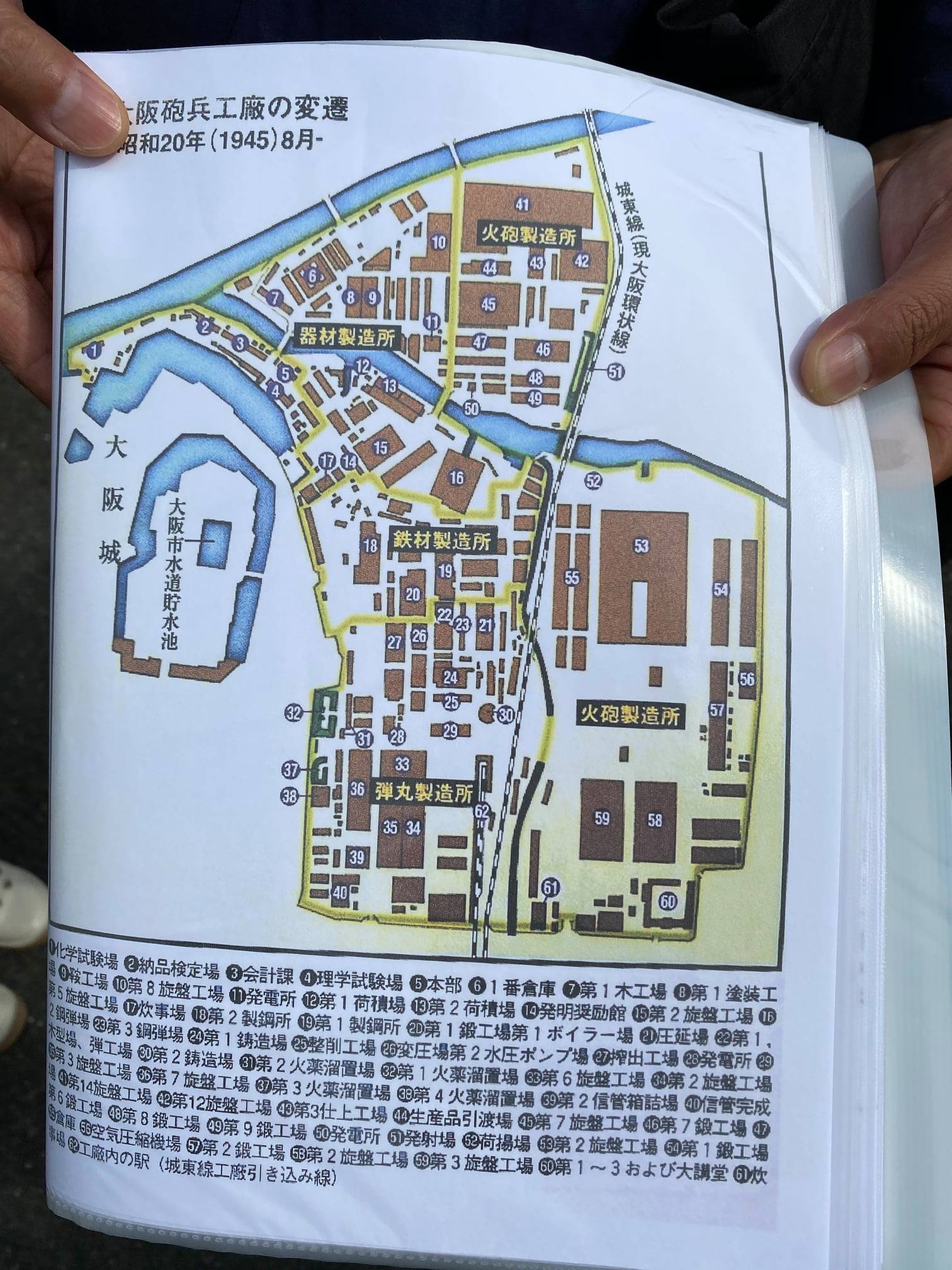

コメント