
『それでも僕たちは「濃厚接触」を続ける!』広瀬浩二郎
コロナ禍以降、濃厚接触について考えている。僕は濃厚接触が好きで、仕事では公私混同をモットーにしているし、メールや電話で済ませられることでも、わざわざ会って処理しようとすることも多い。こちらは何も変わらんのだけど、技術の進化や世間の環境や意識が変わるせいで、「会う」ことの価値が相対的に高くなるということもある。ところが今、会わんよ!と言われる。
CDや配信でももちろん音楽を聴くけれども、ライブにも行く。どちらがどうと言うものではなく、ヘッドフォンで聴く音楽とライブやフェスは、まったく別種の体験だ。配信ライブはリアルなライブの劣化版ではなく、別種のものなので、リアルなライブの代替になるものではない。ヘッドフォンを通しての閉ざされた空間での音楽体験はエナジーの注入に似ているが、ライブやフェスはむしろエナジーの放出だ。エナジーを放出することで、その場所を皆で寄ってたかって祝福する。ライブやフェスは祝祭だ。その祝祭空間で、声も出せない、モッシュもできない、人熱が遮断される。放出どころか、むしろ、エナジーが体内に充満してしまう。皆の中にあってかえって孤独を誘っているような。2人でいるのに心は別々の場所にいるような。それはもはや、濃厚接触ではない。
そうやって考えると、濃厚接触は至るところで忌避されている。ワクチンが行きわたって、コロナをコントロール下に置ける日が来たときにはまた濃厚接触できるさ、という僕らの未来予想図は、楽観的にすぎる気がする。
だって、ライブハウスは、それまでもたないかもしれない。フェスの運営会社は、その日までどうやって食いつなげばいいのか。僕たちは、すでに人前でマスクを外すことをためらいつつある。人前で下着を脱がないように、人前でマスクを外さなくなる日が来るのだろうか? 中東のヒジャブのように、マスクを外す行為はプライベート空間だけ、ということになるのだろうか?
この1年半ほど、そんなことをよく考える。そんなとき、この本に出会った。
著者の広瀬さんは13歳のときに失明し、その後、国立民族学博物館に勤務する准教授だ。みんぱくは従来より、展示物はすべて触れられる博物館で、触る、ということに重きを置いてきた。触れることで得られる情報は、見たり聞いたりするだけよりも、はるかに多いのだから。
また、全盲の人たちにとって、頼りになる知覚は、触覚なのだそうだ。そういえば、点字は指先に触れるエンボスを手がかりに、情報を読み取る。
トーテムポールは、見るものであると同時に、触って理解するために、彫りが入れられている。
京都の龍安寺には、石庭のミニチュアが展示してあり、触れるようになっている。全盲の方は、配置された石をひとつずつ触っていくことで、自分が石を配置する庭師になった気分になるのだそうだ。僕たちが庭を眺めるとき、石の配置などの全体情報は瞬時に自身に入ってくるが、触覚を頼りにすると、ひとつひとつの石の位置情報を順番に得ることになり、時間的な流れが発生する。これが、自分が庭師になって石を配置しているような感覚をつくる。つまり、完成された庭を把握するのではなく、作庭するプロセスが感じられるのが、全盲の方が石庭のミニチュアを触ることで得られる経験なのだそうだ。
琵琶法師は全盲だが、それを聴く聴衆は、目が見える。聴衆がいてこその演奏であり、そこには、盲た人とそうでない人との魂の「濃厚接触」がある。全盲なのだから、聴衆などいてもいなくていいと言うなかれ。彼らは、虚空に向かって平家物語を紡いでいるわけではない。
バードカービングという工芸がある。木製の鳥の模型だが、本物と見間違うほどそっくりにつくられているのは、観賞用としてだけではなく、全盲の方がそれを手にすることで、鳥の何たるかが認識できるようになっているからだ。
この本では、濃厚接触はどのように発達してきたのかの事例がたくさん紹介されており、本の表紙には、点字がプリントされている。
それでも僕たちは「濃厚接触」を続ける。そうせざるを得ない人たちがいて、そのことをスタート地点として、「濃厚接触」の発展的な効用や、一般に知られざる世界を垣間見せてくれる。それを踏まえたうえでのニューノーマルすらが提示されている。
「濃厚接触」が少しずつ忌避されていく風潮にあって、切実に「濃厚接触」を求める人たちがいること。その事実だけで、少し勇気づけられた気がした。この本は、とても沁みた。
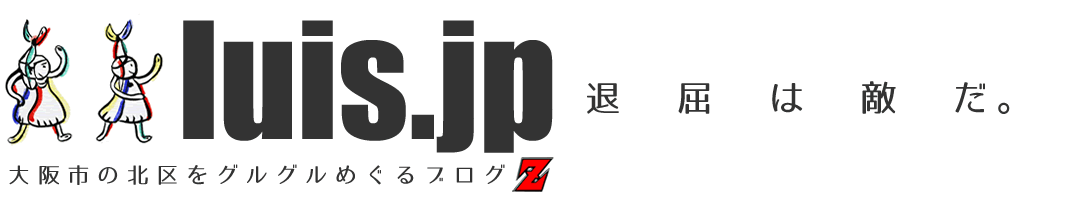



コメント